-
エピソード―わたしと神経発達症
診断・治療について
生活について
周囲の理解について
困っていること
-
大人の神経発達症(発達障害)とは
-
-
自分の特性を知る―医療機関に相談する
-
大人の神経発達症(発達障害)の身近な相談窓口
相談窓口に聞いてきました
-

相談窓口に聞いてきました
当事者会
監修:小坂 浩隆先生(福井大学医学部精神医学 教授)

相談窓口に聞いてきました
当事者会
監修:小坂 浩隆先生(福井大学医学部精神医学 教授)
当事者会について

当事者会は、同じ困難を抱える人同士が支え合う場です。当事者が自主的に集まって、主体的に運営し、自己再生(エンパワメント)を目指す活動であり、ピアサポート、自助グループ、セルフヘルプグループなどとも呼ばれます。
当事者同士で心情や体験、情報の共有ができる、大切な場です。
そこで、これまでに様々な当事者会に参加したり、会やイベントの運営に関わったりしている当事者のみなさんに、当事者会とはどのような場か、どう活用できるかなど、ご経験や考えをお聞きしました。
また、他の当事者会の主催者に向けたセミナーも行うなど、当事者会同士の連携にも取り組んでいる「発達障害当事者協会」と、日本で初めて作られた神経発達症(発達障害)の当事者向けの常設ブックカフェである「Neccoカフェ」の運営スタッフにもお話を聞きました。
お話を聞いたみなさん

発達障害当事者協会
事務局長
嘉津山 具子 さん

発達障害当事者協会 副代表
Neccoカフェ 主催
金子 磨矢子 さん
ほか 当事者のみなさん

Aさん

Bさん
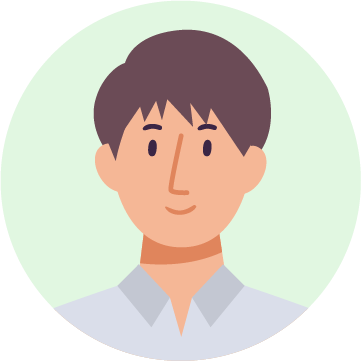
Cさん
イベントや別の会の運営にも
携わる当事者の方々
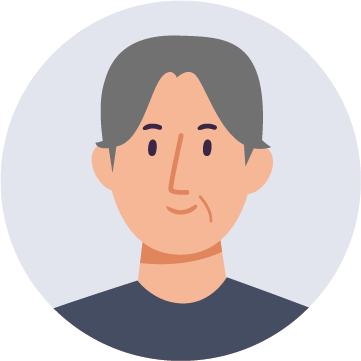
Dさん

Eさん

Fさん
当事者会の活動は様々であり、今回とりあげた内容は一例です。
参加を検討する際は、会の参加条件や活動内容、費用などを確認してください。
-
Q1当事者会とは?
全国にどのような神経発達症(発達障害)の当事者会がありますか?
A1
 嘉津山 さん
嘉津山 さん神経発達症(発達障害)の方の「居場所」のようなところや、相談や情報提供をメインとしている会など様々な会があります。
常設のサロン・カフェや、定期的に集まって話をする茶話会、テーマに沿ったイベント・グループワークなど、形式も様々なものがあります。
常設のカフェは、自由に訪問して交流できる「居場所」のようなところが多いです。
茶話会は、スペースを開放してのんびりと自由に話ができる会や、ファシリテーターが進行してテーマに沿って話をする会などがあります。
リアルに開催する会だけでなく、オンラインでもたくさん行われています。
有志が運営している民間の会が多いですが、自治体や発達障害者支援センターなどがピアサポートの提供をしている地域もあります。
 金子 さん
金子 さんわたしたちの会場では、困りごとやライフハックについて話す会、公務員の会、グレーゾーンの会、男性が恋愛について話し合う会、障害者雇用を考える会など様々なイベントが行われています。
社労士さんに相談できる機会など、専門職への相談会もあります。
また、障害に関する話だけでなく、手芸をする会、映画を語る会、鉄道好きの会など、神経発達症(発達障害)の人が集まって一緒に楽しむ会もあります。
-
Q2参加条件は?
参加するにあたり、条件などはあるのでしょうか?
A2
 嘉津山 さん
嘉津山 さん当事者本人のみの参加に絞っている会もあれば、家族や支援者の参加もOKとしている会、関心がある方まで広げている会など様々です。また、大人のみの会もあれば、小児の保護者向けの会、年齢を問わない会など年齢の範囲も様々です。
そのほか、参加者の範囲・条件を定めている場合もあるので、事前に確認されるとよいと思います。
 金子 さん
金子 さん当事者しかいないから安心して話せる、他の方のご家族が参加していると話しにくいと感じるなど、人によって参加のしやすさは違うと思います。
参加者の範囲を確認して、試しに参加してみたりして、ご自身に合う会を見つけるのがよいと思います。
-
Q3なぜ当事者会に参加した?
どのようなことがきっかけで、当事者会に参加したのですか?
A3
 A さん
A さん何もかもうまくいかず、仕事も辞めて、人生に困っていました。いろんな方面から嫌われている自覚もありました。
医療従事者や支援者、家族には障害がないし、分かり合えるのは同じような境遇の人だけなのではないかと思って、当事者会をいろいろ探しました。
 B さん
B さんわたしは、特性を自覚して診断を受けるか悩んでいた時、オンラインのオープンチャットで情報交換をしました。それは役に立ちましたが、本当はチャットでのやりとりがあまり得意でなく、リアルで直接話す方が話しやすいので、当事者会を探して参加するようになりました。
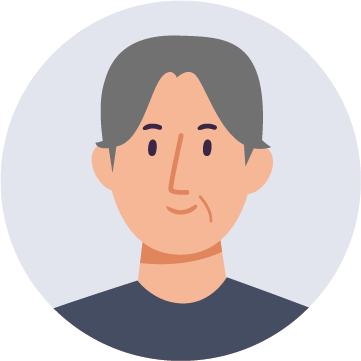 D さん
D さん診断を受けた当時は、ウェブサイトの掲示板などでしか情報を得られませんでした。その中ではじめて自分と似たような人たちがいることを知り、SNSでの交流からオフ会に参加するようになりました。
 E さん
E さんわたしは子どもの頃から、大きな集団に入ることは得意ではありませんでした。
SNSなどで見つけた当事者のワークショップなどに参加していましたが、常設のカフェに行くようになって、神経発達症(発達障害)の人たちとゲームで遊べたらと考えて、ボードゲームのイベントを始めました。仲間を作ろうと思ったのです。
もともとゲームが好きで参加する方もいれば、ゲームの経験はないけれど関心があってやってみたいという方も参加しています。
 F さん
F さん例えば、神経発達症(発達障害)についての本を読んで、書いてあることは分かっても、自分の生きづらさの原因とは思えず、腹落ち(納得)できない人も多いのではないでしょうか。周囲は、自分の生きづらさを深刻に受け止めてはくれないことがあるので、自分と同じような人と会って、生きづらさの正体をつきとめたい、仲間がほしい、自分の居場所や枠組みがほしいと思って参加するのではないかと思います。
-
Q4どんな話をする?
茶話会や相談会などでは、どのようなことを話しているのでしょうか?
A4
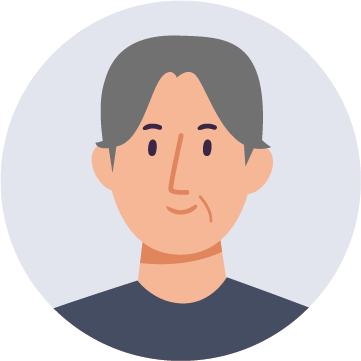 D さん
D さんわたしが運営している会では、仕事のこと、治療のこと、人間関係のこと(職場の上司、女性の友人同士でうまく関係づくりができない)などが挙がります。特に、仕事の面での困りごとが多いと感じます。ライフハックの共有もされています。
 F さん
F さんやはり、人間関係のこと、適職や職場でのサバイバルといった仕事のこと、ライフハックなどがよく話されますが、公的制度の知識・利用、健康問題なども話題になることが多いです。
-
Q5どんな情報交換が役に立った?
どのような情報交換が役に立ちましたか?
A5
 B さん
B さん診断を受けるかどうか迷っていた時、オープンなチャットなどで情報交換をしました。「ADHDあるある」や、検査のこと、医療費の公的な支援制度など様々な情報を得たことが、受診する後押しになりました。
 A さん
A さんわたしは、神経発達症(発達障害)を持ちながら子育てと仕事の両立をするために、様々な公的支援を利用した経験を聞くことができました。周産期を含め、どの段階でどういう支援を利用できたか、という流れを聞いて、具体的にイメージが持てました。
神経発達症(発達障害)に理解のある産婦人科や、子育て・仕事に理解があって行政支援との連携にも取り組んでいる医療機関での経験を聞き、自分が通う医療機関も見直しました。
公的支援の制度に頼ってもいいのか悩んでいましたが、当事者会で、支援制度を活用しながら明るく仕事や生活をしている方々を知って、自分も使える制度を確認してみようと思いました。
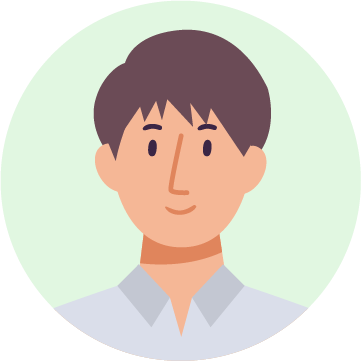 C さん
C さんわたしは、将来を考えるうえで、当事者の方々から、一般雇用、障害者雇用など様々な働き方や考え方を知ることができました。
-
Q6うまく会話に参加できる?
場に合わせて会話がうまくできるでしょうか?
A6
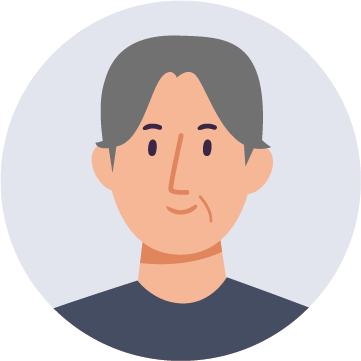 D さん
D さん茶話会では、一人あたり3~5分などと時間を決めて、順番にお話ししていただいています。参加者から出た話題に対して、他の方が共感したり、経験を話したりしてまわしていきます。話さなくてもOKとしています。
オンラインの会では、話す人としての参加だけでなく、聴くだけの参加もできるようにしています。
 F さん
F さん話せない人が出ないように時間配分を定め、ただし無理に話さなくてもOKとしている会が多いと思います。
また、否定や批判、説教をしないようにというルールは設けられていると思います。
 E さん
E さんゲームや創作など何か活動をする会は、自分のことを話さずに当事者と交流する機会なので、まずはそうした会に参加してみるのもよいかもしれません。
 金子 さん
金子 さんわたしたちのカフェでは、「話しかけてください」という意思表示の札をテーブルに置けるようにしていて、話したい人同士の会話が生まれるようにしています。
-
Q7当事者会の選び方は?
当事者会をどのように探したらよいでしょうか?
A7
 嘉津山 さん
嘉津山 さん国が提供している情報検索ツール「ココみて(KOKOMITE)
 」で、各地域の当事者会を探すことができます。
」で、各地域の当事者会を探すことができます。そのほか、当事者の方が各地で実施されているイベントなどをまとめたウェブサイトを利用されてもよいと思います 。
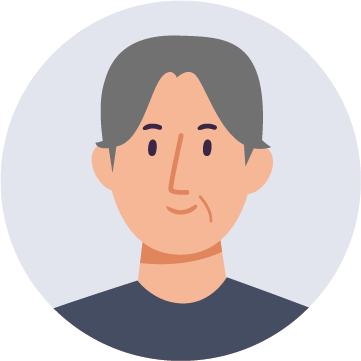 D さん
D さん自分に合った当事者会を見つけていただく機会となるように、他の当事者会の紹介チラシも置いています。
 金子 さん
金子 さん当事者会で話している中で、他の会の情報を得られることもあるのではないでしょうか。
興味があればいくつか参加してみて、自分に合う場を見つけて自分なりに参加していくのがよいのではと感じています。
 F さん
F さんウェブサイトやSNSで、どのような活動をしているかなどを紹介したり、会の告知や、どんなことが話されたかなどの開催報告を載せたりしている当事者会もあります。
もちろん、ホームページなどがなくても、きちんと開催している会はあるのですが、事前に知ることで、安心して参加できるという方もいます。
 A さん
A さんあまりにも非公式な印象を受けたり、会の歴史が浅かったりする会は避けるようにして、運営がしっかりなされている会を選ぶようにしています。
わたしは、医療機関で当事者会のリストをいただいて、参考にしました。
-
Q8参加にあたって守ることは?
参加にあたって守ることなどはありますか?
A8
 嘉津山 さん
嘉津山 さん会によって、条件やルールを設けていることが多いので、必ず確認して参加することをお勧めします。
個人情報を含めて、会で話されたことを外で話したり、オンラインで書き込んだりなどは禁じている会が多いです。会以外での交流でも、ルールが設けられていることがあります。
また、あくまで当事者会は、当事者同士の支え合いの場であるため、医療・福祉・行政などの支援が必要であると考えられる深刻な状況の場合は、まずはそうした支援を受けられるよう勧めています。
 金子 さん
金子 さん攻撃的な言動・行動をしたり、特定の相手に一方的に固執して個人的な関係を作ろうとしたり、勧誘をしたり、という行動は避けるように促しています。安心な運営が守られなくなる行動があると、ルール上、残念ながら、次から参加ができなくなってしまうこともあります。
-
Q9トラブルが心配・不安ですが。
何かトラブルなどがないか、心配があります。
A9
 A さん
A さんわたしは、本名を含めて個人情報を伝えたり、連絡先を交換したりするのは避けています。
 F さん
F さんハンドルネームでの参加としている会が多いと思います。
 B さん
B さん会話でつい熱くなってしまうことはありますが、コミュニケーションでトラブルなどになったりしたことはありません。
 嘉津山 さん
嘉津山 さん確かに、もめごとや、当事者同士の個人的なトラブルなども以前はよく聞かれました。
円滑な運営を目指して、当事者会の主催者向けの研修で、運営者同士で情報交換しています。そうした会では、工夫もあってかあまり聞かれなくなってきたと思います。
 金子 さん
金子 さん話す中で、少し意見がぶつかることがあるかもしれませんが、お互いを尊重して乗り越えていく過程を経験することも大切だと思っています。
-
Q10参加の費用はかかる?
会に参加する際、費用はかかるのでしょうか?
A10
 嘉津山 さん
嘉津山 さん会によって異なりますが、会を開催するためには、公民館などの会場を借りるための費用などの工面が必要です。そのため、参加費制の会は多いと思います(例えば1回あたり300円、500円など)。
店舗などで開催する会などでは、参加費やドリンク代などが必要なこともあります。
また、初回はお試しで無料参加として、継続して参加する場合に会費制とする会など、各会によって工夫しているようです。
-
Q11参加してよかったことは?
参加して、どのようなことがよかったですか?
A11
 B さん
B さん当事者会では、同じ境遇の人がいて共感できること、ロールモデルの人と話せること、困りごとの相談ができることが大きいです。普段の生活では、ロールモデルにできる人に出会えませんでした。
 A さん
A さんわたしは、180度価値観が変わりました。働き方、家族・子どもを持つこと、公的な支援サービスを使うことなど、賛成・反対と様々な意見を聞けるからです。どうしてそういう意見を持っているのだろう?と考え方や背景を知ることができます。
一方的に決めつけたり、否定しあったり、どちらが正しいかを争う場ではないことがいいと思います。
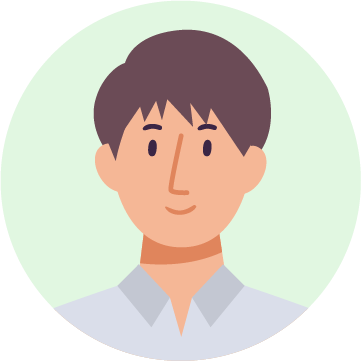 C さん
C さんウェブや本の情報は確かに役に立ちます。でも、そうして社会に発信・還元しているような、活躍している方の言葉は、自分に当てはめられず納得できない時があります。
しかし、当事者会に来ると、多くの考え方に出会えるので、自分とのつながりが感じられて、包摂されていることを実感します。
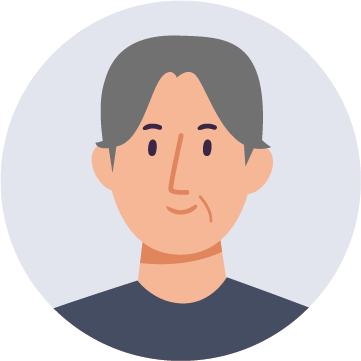 D さん
D さん自分の話を聞いてもらっているうちに、課題が整理できた、言語化できた、という方はよくおられます。そして、次は相談したい内容をまとめて来ます、とまた参加してくださいます。
 F さん
F さん例えば、「雑談が苦手」といった困りごとは、医療や福祉の支援者には相談しにくいです。当事者だからこそ共感できる「あるある」や「困りごと」を話せます。
 E さん
E さん誤った情報が流布されていて、それを鵜呑みにしている方もたまにおられます。当事者同士の交流は、誤りを知ったり、正確な情報源などを知ったりできる機会であると思います。
 B さん
B さん最初に話した時に暗い表情だった方が、参加を重ねてだんだん少し明るい表情に変わっていくのを見た時に、うれしく感じました。
-
Q12当事者会はどんな場?
当事者会は、みなさんにとってどのような場でしょうか?
A12
 B さん
B さん自己理解を深められる場、自分を見つめることができる場だと思います。生きて暮らしている当事者の方と直に接して得られる生の情報は、本やウェブなどとは、情報量が圧倒的に違うと感じます。神経発達症(発達障害)のない方であれば、わざわざ向き合ったり言語化したりしなくてよいことなのかもしれません。
他の当事者と関わりながら受け取る情報から、時には少しぶつかることがあったり、鏡になったり、反面教師になったりしながら、自分の特性を知って理解し、客観視できていくと思います。
 F さん
F さん安心・安全に自分の言葉でお互い話せる場であり、擬態を脱いで自分のままでいられる場だと思います。
今、必死であがいている段階の方にも、様々な制度を活用したりして困りごとを軽くしながら明るく過ごせるようになった段階の方に出会える場所であるのはよいと思っています。
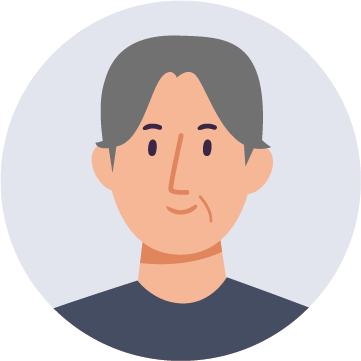 D さん
D さん家族にも誰にも話せない、つらい気持ちを話せる場だと思います。
生きづらさのすべてを解決することはできないかもしれませんが、少しは解決に向かって進められる場と考えています。
 A さん
A さん自分の人生の選択にあたって、情報を得たいと思っても、医療や福祉の支援者からの情報は、正しいけれど実際に自分には当てはまらない正論、理想論と感じてしまうこともあります。
理想論ではなく、神経発達症(発達障害)である当事者自身の人生経験からの、現実的な情報を得られる場だと思います。
自分自身も、他の方が選択する際にオプションとなる情報を提供できればと思っています。
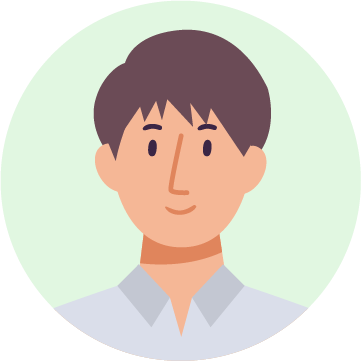 C さん
C さん自分を相対化できて、独りよがりにならずに済む場所だと感じます。
自分一人では考え方が限られますし、たくさんの意見や目の中で、この見方もある、と知ることができます。
自分はどういう働き方を選ぶべきなのか、と考える時も、自分の前にも後ろにも多くの誰かがいてくれる気がします。
-
Q13参加を考えている方へのアドバイス
これから当事者会への参加を考える方にアドバイスをお願いします。
A13
 嘉津山 さん
嘉津山 さん初めて参加される方は、居場所のような会、いわゆる常設のカフェや、地域ごとの茶話会などから始めてみるとよいかもしれません。だんだん自分の課題が分かってきたら、テーマ別の会に参加するのもよいと思います。
地域の会では、参加場所を非公開にしていることもあります。近くに会がない場合や、近くの会を避けたい場合などに、都市部などの会を訪れてみる方もいます。また、オンラインの会を利用してみるのもよいでしょう。
 B さん
B さんどん底の自分、ショックを受けている自分でも、受け止められて、そこにいられる場だと思います。
診断後はショックを受けて、障害を受容したつもりでも、また壁が現れたりして、受容の過程は続いていくものだと思っています。
当事者会には、自身の障害に向き合う様々な段階にいる方がいます。
もし、今は悲観的で、今後もっと悲観的になることもあるかもしれないとしても、ありのままでいい場だと伝えたいです。
 金子 さん
金子 さん毎日のことに必死で常に疲れている当事者の方が多いと感じています。少しでも気をつかわずに、安心してほっとできる場所になればとカフェを作りました。
そうした場所が日本中にたくさんあれば、と思います。
当事者の集まりは、気の合う人ばかりではない時もあるかもしれません。心の拠り所となる場所や人は、どこか1つだけに頼りすぎるのでなく、たくさんあることが大切だと考えます。一人でも多くの当事者の方が、自分なりの楽しみや行きたい場所が増えることを願っています。